父をフォロー
まだ始まって間もないこのサイトですが、父をちょっとフォローしたいと思います。
あちこち開いて読んで下さった方には
「言いたいことをスパスパっと言い切る父親」という冷たい印象を与えたかもしれません。
いえ、別に、うちに「お嬢さんを嫁に」と挨拶に行くわけではないのでそれでもいいんですが。
それはわたしの17歳の誕生日。
勤めから帰ってきた父が
 、これといった愛想もなく渡してくれたのは本屋さんの袋でした。
、これといった愛想もなく渡してくれたのは本屋さんの袋でした。「なになに!?」と開けて出てきたのは
 (現物。ビニール製テーブルクロスの上に置いてベラっとはげた傷あり)
(現物。ビニール製テーブルクロスの上に置いてベラっとはげた傷あり)フランス女流作家サガンのセンセーショナルな処女作「悲しみよこんにちは」。
ジーン・セバーグが主人公セシルを演じた映画もすてきでした。
避暑地でのキュートなサブリナパンツ姿と、そのベリーショートの髪型に魅せられて
当時いったい何人の日本人女子が、美容師さんと気まずい空気になったことでしょう。
わたしも、サガンの名前と、この小説のうわさはきいたことがありました。
本裏面のあらすじを目で追って内容を確かめていると 
 母が登場。しかし
母が登場。しかし 姉登場。しかし
姉登場。しかし  「『あの』おとうさんがナゼ!」
「『あの』おとうさんがナゼ!」

 母が登場。しかし
母が登場。しかし 姉登場。しかし
姉登場。しかし  「『あの』おとうさんがナゼ!」
「『あの』おとうさんがナゼ!」 「・・・・・・・・・・」

本の裏書きから内容をかいつまんで。
「若く美貌の父親の再婚を、父の愛人と自分の恋人を使って妨害し、聡明で魅力的な相手の女性を
死に追いやるセシル。・・・(略)・・・青春期特有の残酷さをもつ少女の感傷にみちた好奇心、
愛情の独占欲、完璧なものへの反発などの微妙な心理を描く・・・」
父の愛を独り占めしたいがために、思いつく限りの大人びた策を弄すセシル。彼女が「その夏わたしは17だった」という設定なのでした。
うちは、S賀市の、まだまだ田んぼが広がる、
夜友だちと電話していると「ねえ、何の音?」ときかれるぐらいカエルの声がヒビキわたる
新興住宅地のごくごくフツーの家。
封建的・保守的な田舎の一家族。
父は「聖人君子」というか、「色」とか「情」とか「欲」(あえてバラバラにしました。好きなように組み合わせて下さい。)を全っっくにおわせないひとで、
娘たちの「女性化」を、さびしさというより嫌悪感を持ってみていたような印象すらあります。
友だちも少なく、お酒も飲まず、
趣味は読書とパチンコとゴルフの打ちっぱなし。
いわゆる、戦後の経済成長期を生き抜いてきた企業戦士といっていいかもしれません。
いつもピリピリしていて、思春期の娘にとっては「極力避けたい」存在。
その、お、お、おとうさんが。こんな情愛まみれの 。しかも父と娘が題材の。
結局、女三人組は
「本屋さんで『娘が17の誕生日』て相談して、店員さんに選んでもらいんさったとやろ!
どがん話か知りんさなかとさ!ハッハッハ」
(注:選んでもらったのだろう。どんな話か知らないのだ。)と、
この父の理解し難い買い物を、笑いで噛み砕いたのでした。
でも、こんなふうに父個人から直接贈り物というのは、お年玉以外では後にも先にもこの一回きり。
かすかな謎を残したまま、それは青春時代の忘れ難いひとコマ。
それからン十年たった今年のお正月、わたしは実家の本棚で探し物をしていました。
すると、出て来たのは旧仮名づかいの古い古い数冊の文庫本。
昔は自分の名前を本に書いていたのでしょうね、一冊目には旧姓の母の名前が。
ということは、結婚するときにも持ってきたお気に入りの本ということか?
そしてボロっボロの二冊目はなんと堀口大学訳「ヴェルレエヌ詩集」。
ヴェルレーヌって、あの教科書の上田敏訳海潮音?、「秋の日の ヴィオロンの・・」の!?
えっ、おかあさん、フランスの詩人とか興味あったわけ?初耳やけど...と裏表紙の名前を見ると
そこにはいつもの几帳面な筆跡で、父の名が。
幼い頃住んでいた社宅には、可愛い庭がありました。
昨今の「ガーデニング」にはほど遠いしろものですが、
不器用にレンガで仕切られた花壇には、バラやデージーの隣にシャクヤクやボタン。
和洋折衷(何でもありとも言う)で、季節の花があちこち好き勝手に咲いており、
サルビアの蜜を吸ったり、おしろい花の種を割って中の白い粉を顔に塗ろうとしたり、
可愛い花が必ずしもいい香りではないことを知ったり、
小さい女の子の小さい好奇心を満たすには絶好の空間だったのです。
その庭を作ったのは、問わずもがな専業主婦であった母だと、わたしはずっと信じていました。
つい最近、母と昔話をしていて「水ヶ江の庭、良かったよね〜  」
」
 」
」


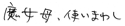
出た。
あの、大小さまざまな花の咲く思い出の庭は父の手によるものだったのです。
父は、少なくともわたしが17歳の時点で、
家族の誰より頭のなかがモダンで、ロマンチストだったのです。
ひょっとしたら(妄想)
十代でヴェルレエヌに心酔した青年は、やがて結婚し、娘が生まれ、
「この子が17歳になったら『悲しみよこんにちは』をプレゼントしよう」と
彼のダンディズムをさりげなくプレゼンテーションする機会をうかがっていたかもしれません。
それがまさか
「お父さんどーしちゃったんだろう」と皆を不安にしようとは。
おかげ様で父はまだ健在です。でも
このことを、今になって父に確認するのは
野暮のうわぬりのような気がしています。
「思い込み こんにちは」ではありませんように。
2009年5月23日土曜日